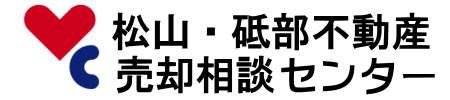Q:隣の家との境にブロック塀があります。どちらのものですか?
ご近所やご自宅にもあるブロック塀ですが、これ、いったい誰が所有しているものなのか、皆さんはきちんと把握していますか?お隣さんとの境界を示すためのブロック塀ですが、自分たちのものなのか、はたまたお隣さんのものなのか、分からないということが実は意外に多いもの。そこで今回は、「ブロック塀は誰のものなのか」、また、「どちらのものかはっきりさせる必要があるのか」について説明していきましょう。
ブロック塀はお隣さんとの境界線
お隣さんと自分の家の境目に建っているブロック塀が、隣地との境界線を表しているということは容易に想像がつきます。では、もう少し細かく見ていきましょう。すると、「ブロック塀の分も含めた面積が自分たちの土地なのだろうか」、あるいはその逆に「ブロック塀はお隣の敷地の端に建てた目印なのかも」という疑問にたどり着くはずです。
細かくて難しい問題のように見えますが、実は、「ブロック塀のちょうど真ん中が境界線」というケースが意外に多いのです。「そうなると、ブロック塀自体はどちらの所有物なの?」という疑問が湧いてきますよね。ここが意見の分かれるところなんです。
「昔からこの塀はお互いのものだという決まりになっている」と双方が納得しているような場合は問題ありません。しかし、なかにはお互いがそれぞれ「この塀はうちのものだと聞いている」と譲らず、トラブルに発展してしまうケースもよく見受けられます。
そんな時は、改めて測量図を調べてみることです。それでもはっきりしない場合は、再度測量をやり直して、どちらのものかはっきりさせたほうが良いでしょう。
しかし、所有が明確になってもその結果に納得が出来ず、新たな火種となってしまうことも少なくありません。
そういったトラブルを防ぐために、近年新しく建てられている住宅ではこのような「境界線の真上にブロック塀やフェンスを設置する」という昔ながらの方法は取られていません。きちんと測量をして自分の敷地内に新しいフェンスや塀を設置します。
覚書を残しておこう
誰の所有なのかわからずにトラブルに発展するケースは塀だけではありません。皆さん「私道」はご存じだと思います。街中では「私道につき進入禁止」や、「ここから先は私道です」などという看板を見かけることがよくありますよね。
私道とは「本来は誰かの所有する土地を、道路として使用している場所のこと」を指します。そのため、私道を日常的に使用させてもらわなければならないような場合、「車を出し入れする際に通過することを許可します」などといった内容の覚書を交わしておくことが通常です。
しかし、この私道も先ほどのブロック塀同様、長年使用しているうちに本当の所有者の存在があやふやになってしまい、地域の人が「ここは昔からみんなで使っていたから共有の土地なんだ」と勘違いしてしまうこともよくあります。そのままではトラブルの元となりかねませんから、謄本を調べて所有者を特定し、所有者と使用者の間で覚書を交わすことで今の状況を整理する必要があるのです。
前述のブロック塀の件に戻りますが、測量などの後、どちらの所有かがはっきりしても、すぐに塀を取り壊す必要はありません。お互いの了解に基づき、「将来建物を建て替えるときに正しい位置に設置しなおします」といった主旨の覚書を交わしておくのが望ましいでしょう。
土地を売却する際は、今回お話したブロック塀や私道であっても、「誰のものかイマイチはっきりとしない」という状態のままでは買主様に引き渡すことはできません。あらかじめ境界線や所有者を明確にするのは売主側の責任となるため、売主様は仲介手数料などに加えて測量にかかる費用も負担しなければなりません。物件を預けた不動産会社が誠実な会社なら、これらの売主様負担の費用についてもあらかじめ説明があるはずです。